科学と伝統が証明する、調和の微生物
マコモ菌の科学的な正式名称は「バチルス・サブチルス・ON-1」です。
この「ON」は、マコモの研究に60年以上を捧げた小野寺廣志氏の名に由来します。
小野寺氏は、古来から日本人に親しまれてきた真菰という植物の中に、驚異的な生命力を持つ微生物が存在することを発見しました。
マコモ菌の最も注目すべき特性は、極限環境での生存能力です。
400度の高温でも死滅せず、強い酸性やアルカリ性の環境でも生き延びることができます。
さらに、胃酸にも耐えて腸まで届くため、腸内で確実に働くことができます。
マコモ菌のケイ素的アプローチも見逃せません。
ケイ素は体内のあらゆる組織に存在し、細胞同士をつなぎ、修復を促進する働きがあります。
マコモ菌は、このケイ素の働きをサポートし、細胞レベルでの調和を促進します。
骨や血管、肌、髪など、体のあらゆる部分の健全性を保つために、ケイ素とマコモ菌の組み合わせは理想的なのです。
一般的なプロバイオティクスは、特定の善玉菌(乳酸菌やビフィズス菌など)を増やすことで腸内環境を改善しようとします。
しかし、マコモ菌のアプローチは全く異なります。
善玉菌、日和見菌、悪玉菌という腸内細菌の三大グループすべてのバランスを調整し、生態系全体の調和を図るのです。
この「調和の力」は、腸内だけでなく、心身全体に影響を与えます。
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内環境が整うことで、セロトニンなどの神経伝達物質の産生が正常化し、精神的な安定がもたらされます。
実際に、マコモを継続的に摂取した方々から「気持ちが穏やかになった」「イライラしなくなった」という声を多数いただいています。
キララサロンでは、マコモをお料理やスイーツに使用しています。

あきちゃんの発酵調理において、マコモ菌は欠かせない存在です。
マコモを加えることで、料理の味わいが深まり、消化吸収がよくなります。
お客様からは「体が軽くなった」「お腹の調子が良い」という感想をいただいています。
空間浄化におけるマコモの活用も重要です。
マコモを培養した水を空間に散布することで、微生物のネットワークが形成され、空気質が改善されます。
特にキララの塗り壁にマコモ水を散布することで、唯一無二の癒し空間が完成します。
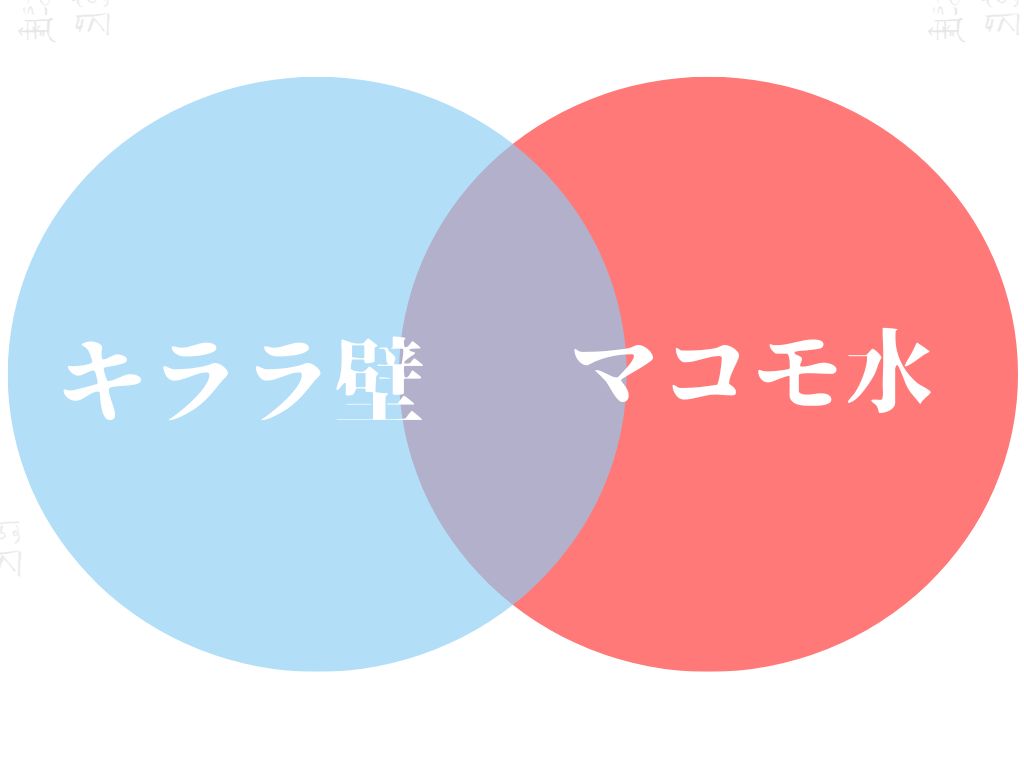
寝室にマコモ水を散布して眠ると、朝の目覚めが爽やかになるという報告もあります。
興味深いのは、マコモを生活に取り入れた方々が体験する「シンクロニシティ」です。

思いがけない良いご縁が続いたり、必要な情報が自然と入ってきたり、直感が冴えたりという現象が報告されています。
これは、マコモ菌が作り出す「菌ネットワーク」による合気力ではないかと考えられています。
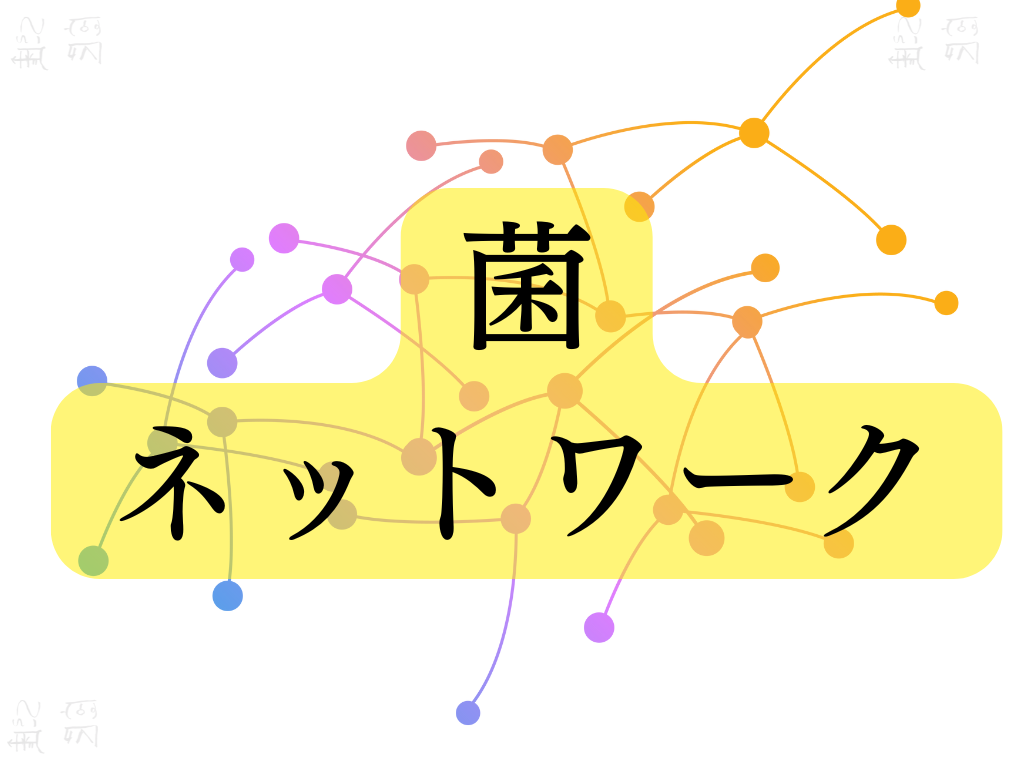
微生物学の最新研究では、微生物同士が化学物質を介してコミュニケーションを取り合い、複雑なネットワークを形成していることが明らかになっています。
マコモ菌もまた、このネットワークの調整役として機能し、人間の意識や行動にまで影響を与えている可能性があります。
古事記に記された因幡の白兎の物語では、真菰の穂で作った布団に包まれたことで白兎の傷が癒えたとされています。この神話が示すように、マコモの治癒力は数千年前から認識されていました。
出雲大社では毎年6月1日の涼殿祭で真菰が使用され、神聖な植物としての伝統が今も受け継がれています。
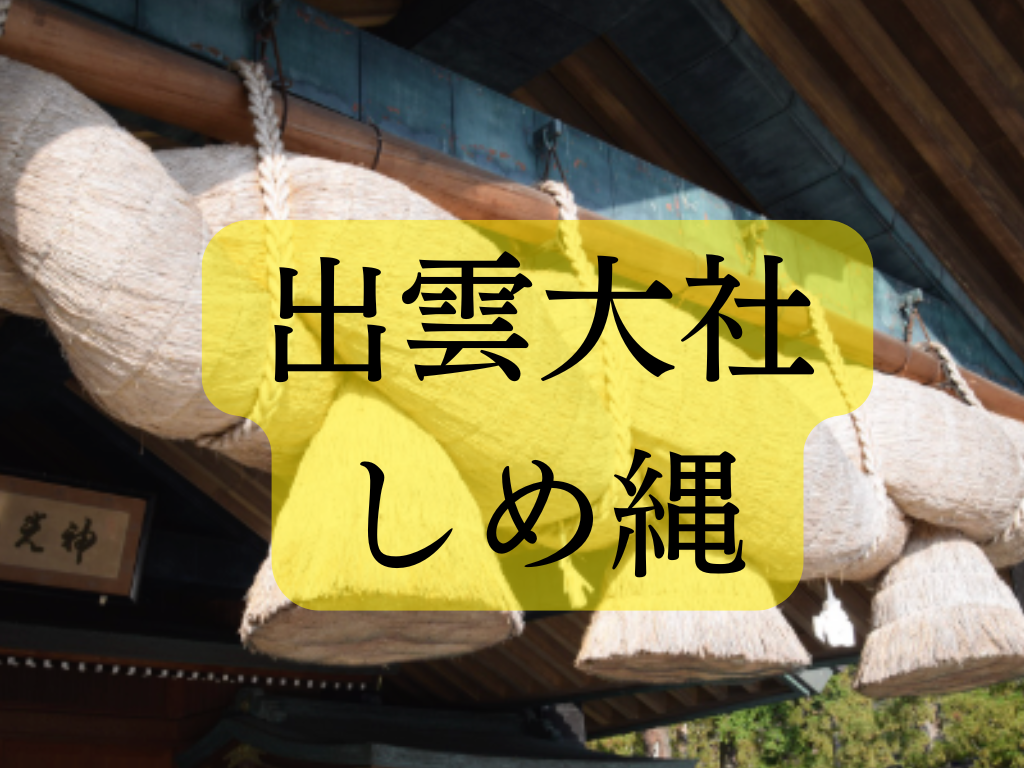
現代における水質浄化への応用も注目されています。琵琶湖や霞ヶ浦では、マコモを使った水質浄化プロジェクトが実施され、化学的汚染に対する生物学的解決策として成果を上げています。
キララサロンでは、このマコモ菌の力を最大限に活用し、来られる方々の心身の調和をサポートしています。

マコモ菌は、私たちが目指す「人間パワースポット化」の核心であり、愛と融和のエネルギーで世界を包み込む可能性を秘めているのです。