持続可能な未来を創る、生態系農業の最前線
協生農法は、従来の農業が抱える環境破壊や生態系崩壊の問題に対して、自然の生態系メカニズムを農業に応用することで解決策を提示する革新的アプローチです。
森林生態系をモデルとし、多品種の植物を混植することで、土壌改良や病害虫防除を自然の力で実現します。
キララサロンが今後提携していく宇陀市の農園では、協生農法指導者の森哲也さんが中心となって、耕作放棄地を豊かな「食べられる森」へと変えていく壮大なプロジェクトに取り組んでいます。
2メートル間隔で配置された果樹を中心に、その足元には様々な野菜やハーブが共生し、水辺にはマコモやクレソンが育ち、立体的な多層構造が形成されています。

※森哲也さんの農園風景
この農法の科学的根拠は、群集生態学や生態系生態学の研究成果に基づいています。
多様な植物が共存することで、単一栽培では避けられない連作障害が自然解決され、土壌微生物の多様性が高まることで、年々土壌が肥沃化していきます。
実際に、協生農法を続けている圃場では、開始から数年で土壌有機物が増加し、保水力が向上するというデータも報告されています。
防災の観点からも、協生農法は重要な役割を果たします。
多様な植物の根が複雑に絡み合うことで、土壌の団粒構造が発達し、豪雨時でも土壌流出を最小限に抑えます。
深根性の植物と浅根性の植物が組み合わさることで、地表から深層まで土壌が安定し、土砂災害のリスクを大幅に軽減します。
また、森林のような多層構造が雨水を緩やかに地中に浸透させ、洪水を防ぐとともに、渇水時には地下水を涵養する役割も果たします。
さらに、化学肥料や農薬を使用しないため、河川や地下水の汚染を防ぎ、下流域の水環境保全にも貢献しています。
ムクナ豆は、この協生農法において特に重要な作物です。

強力な窒素固定能力により、化学肥料を使わずに土壌を豊かにする働きがあります。
地上部が繁茂することで雑草を抑制し、深く張った根が土壌を耕す効果もあります。
栄養面でも注目すべき特徴があります。
ムクナ豆には、脳内神経伝達物質ドーパミンの前駆体であるL-ドーパが豊富に含まれており、インドの伝統医学アーユルヴェーダでは「神経の強壮剤」として古くから使用されてきました。
現代医学でもパーキンソン病の治療薬として研究が進み、天然の形で摂取できる食材として再評価されています。

協生農法で育った作物の最大の特徴は「野生エネルギー」です。
化学肥料による急速な成長ではなく、自然のリズムでゆっくりと育つため、細胞壁がしっかりしており、栄養素が凝縮されています。糖度計で測定しても、慣行農法の野菜より高い数値を示すことが多く、味の濃さを実感していただけます。
キララサロンでは、この協生農園での収穫体験イベントも定期的に開催しています。
裸足で大地を踏みしめ、自分の手で野菜を収穫し、採れたての食材をその場で味わう。
この体験は、食べ物がどこから来るのかを実感し、自然への感謝の気持ちを呼び起こします。
協生農法は、気候変動対策、生物多様性保全、食料安全保障、そして防災を同時に達成できる未来の農業として、国際的にも注目されています。

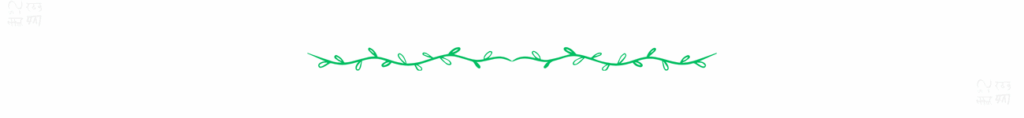
【協生農法指導者:森哲也さんプロフィール】
協生農法の理論と実践を深く学び、奈良県宇陀市の耕作放棄地を「食べられる森」へと再生するプロジェクトを主導。従来の管理型農法ではなく、動物、植物、微生物をパートナーとして、人間がほとんど手を加えない農法技術を実践。150種類以上の作物が共生する農園で、食料生産と生態系再生を両立させる先進的な取り組みを行っている。キララサロンでは、この協生農園で採れた作物を発酵調理に使用し、参加者には収穫体験や農法の学びを提供している。
